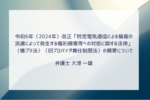インターネット上の投稿を理由として契約者情報の開示請求がなされると、プロバイダから意見照会が届くことがあります。
さらに手続が進んで開示請求が認められると、プロバイダから開示請求者に対して契約者情報が開示されます。
この際プロバイダから「発信者情報開示のお知らせ」が届きますが、このお知らせには裁判所の管理番号(事件番号といい、発チ○番などと記載されています。)が記載されています。
こうしたときに、開示請求に係る裁判所の記録を確認したいがどうすればよいか、というご質問をいただくことがあります。
ここではこの点を解説します。
目次
1 「発信者情報開示のお知らせ」とは何か
前提である「発信者情報開示のお知らせ」については、こちらの記事をご確認ください。
2 記録の保存先の確認
まず裁判記録を保管している裁判所がどこかであるかを知る必要があります。
「発信者情報開示のお知らせ」には、事件番号のほか、裁判所名が記載されていることが多いことから、これにより裁判記録がどこにあるかを確認することができます。
裁判管轄との関係で、多くの場合は霞が関所在の東京地方裁判所民事9部(ただし著作権等の知的財産関係については目黒庁舎)となります。
3 閲覧謄写ができるのは利害関係人だけ
開示請求に係る裁判記録は誰でも閲覧謄写できるものではありません。
いわゆる情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)12条1項では「当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は発信者情報開示命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。」とされています。
「当事者」とは開示命令事件の申立人(インターネット上で権利を侵害されたと主張する方)と相手方(プロバイダ)となるため、「発信者情報開示のお知らせ」が届いた方は裁判との関係では「第三者」となります。
ここで「利害関係を疎明した」とあるため、無条件で閲覧することはできません。
これに該当するのは典型的には発信者や意見照会を受けた者とされています(「一問一答令和3年改正プロバイダ責任制限法」Q65(商事法務))
そこで、意見照会書や発信者情報開示のお知らせなどを疎明資料として裁判所に提出することで、利害関係を疎明して、閲覧謄写をすることとなります。
4 まとめ
いうまでもなく裁判記録の閲覧謄写をしても問題解決にはなりません。
仮に発信者として特定されたことに心当たりがある場合には誠実な対応が求められています。